企業の社会責任
マンハッタンのデパートのショーウィンドーでは数千万円もかけるホリデーシーズンの飾り付けが始まりましたよ。ハロウィンが終わるとあとは一気に感謝祭からクリスマス、そんでもってニューイヤーへ、とせわしない感じがするのはこちらでも同じですね。
さて、生き馬の目を抜くような厳しい商戦が展開するアメリカなんですが、一方で今年は「コーズ・リレーテッド・マーケティング(CRM)」という商法が注目されました。企業が社会貢献をうたってそれを販売促進につなげるというもので、この手法でのマーケティングが今年は昨年より20%以上増えて13億4千万ドル(1600億円)規模にもなるというのです。
「コーズ(cause)」というのは、社会の共通目標・大義といった意味です。日本語になりにくいし学校じゃあまり教わりませんが、けっこう使う英単語です。CRMには売上の一部を非営利団体の活動などに寄付したり、ボランティア活動などを奨励・後援したりする活動も含まれます。そうした大義に則って社会的問題を解決する姿勢を取ることで企業のブランド力が高まり、同時にその「コーズ」に共感するような社会意識の高い消費者を開拓することもできる。単なる寄付活動とも違って、問題解決を目指す公益セクターともマーケットを通じてつながることができる利点もあるようです。つまり、単なる慈善事業というのではなくて、その“善行”を販売戦略とうまく絡ませる手法、というわけですな。
そういえば先月は「乳がん啓発月間(breast cancer awareness month)」でした。タイムズスクエアのビルボードでもシンボルカラーのピンク色の啓発広告が目立ちました。キャンベルスープの赤い缶詰がピンク色になったり、ハードロックカフェがピンク色のピンを配ったりポラロイドがピンクのカメラを出したり、ほら、ぜんぶ自分のところの商品と関係づけたり販促とつなげたりしてるでしょ。昨年のハリケーン・カトリーナ災害ではFedexやMTVなどの企業が共同でキャンペーンを張ってボランティアを募り、休み期間の大学生らを大量にニューオリンズなどに送り込んだなんてこともありました(でもFedexって同性パートナーになんの保障もしてないわりとアンチゲイな企業です)。アップルがiPodの赤を発売してその売上の10ドル分をエイズ基金に寄付するという手法なんかはまんまズッポリとこれにあたりますよね。これは大人気で新たに8GB版も出したというニュースがまだ新しい。じつはこれ、「(PRODUCT)RED」というキャンペーンにアップルがのっかったもので、他にもアメックスの赤いカードとか、モトローラの赤い携帯とか、コンヴァースのシューズとかエンポリオ・アルマーニの赤い時計とかもあるんですわ。企業が乗り出すとほんとに社会の注目度が上がるし、それに顧客も応えるという双方向のコミュニケイティヴな関係がだんだん出来上がりつつある、という感じでしょうか。
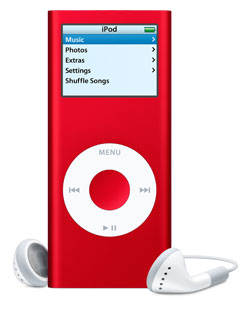

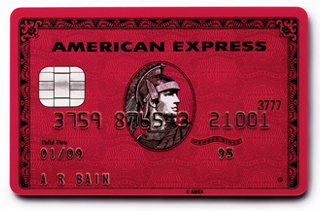
「13億ドル」というのは昔からあるスポーツ大会などのイベントスポンサー・マーケティング(冠大会とかです)の1割ほどの規模しかないのですが、こちらのスポンサー費の伸びがこのところ減少に転じているので、いずれCRMは企業からの強いメッセージ性を武器に遜色ないほどに重要な位置を占めてくると思います。イベントの冠って、あまりメッセージないですものね。
で、それを裏打ちするようにアメリカの次代を担う若年層が、けっこうこのCRMに反応しているって調査が今月になって出たんですね。
ボストンのリサーチ会社Cone & AMP Insightsってところから出されたアンケート結果なんですが、調べでは若年層の90%近くまでが社会問題の解決に積極的な企業ブランドの商品を購入したいとこたえてるんですって。
全米の13歳から25歳までの1800人に調査した結果で、この世代は2000年に成人(米国では21歳)となった1979年生まれから2001年に生まれた子までを含め、新世紀を表す「ミレニアルズ millenials」または「ジェネレーションY(Gen Y=Y世代)」とも呼ばれます。この世代とコーズ・リレーテッド・マーケティング(CRM)の関係を探ったわけですわ。
その結果、61%の回答者が自分は世界をよい方向に変革するのに責任があると考えており(すごい!)、同時に78%までが企業もその努力に加わるべきだと信じていると。また、ある企業がそうした社会の共通問題の解決や正義(コーズ)の実現に深く関わっているとわかった場合、75%の回答者がその企業の広告に注目するとし、90%までが、そうではない企業からコーズに関与している企業ブランドへの乗り換えを行う、と答えてるんです。
ほかにも、商品を買うときに69%がその会社の社会問題と環境問題への取り組みを考慮すると答え、66%が友人にもそういう企業のものを買おうよと勧めてるんだっていいます。
若者らしい(?)正義感に燃えた回答ですね。ってことはこれから年を取って次第にスレちゃって、そんなこと関係なくて安いもんがいいって思うようになるかもしれないってことだけど、ま、ここではね、こういう調査が出てこういう結果がアナウンスされて、それで企業がそういう方向にまたややプッシュされるということが面白いのであって。
先ほど触れた(PRODUCT)REDもそうですが、北米と英国に600店舗以上を持つ「アルドー」っていう靴屋さんチェーンがあって、そこでは昨年度から長期にわたって「エイズと戦うアルドー」キャンペーンを展開してます。若者に訴求するためにオスカー俳優のシャーリーズ・セロンやエイドリアン・ブローディ、人気シンガーのジョン・メイヤーやルダクリスらを起用してエイズの現実を直視する「聞く、見る、話す」っていうキャンペーンをやっているんですが、これがやはり成功しているらしい。

企業が社会公共活動にまで目配せをするというのは確かに余裕のあるアメリカ資本主義ならではの話です。日本ではまだまだというか、そもそも社会事象にあまりに関心がない、あるいは、そういう“政治的”なことには商売はあまり首を突っ込まないという通念のせいかもしれませんね。CRMという新しいトレンドは、そういう“因習”とは逆のところ、つまり減点を気にする消極的なマーケティングではなく、得点主義の積極的なマーケティングにあるわけですから。
これはじつはLGBTマーケットに向けたアメリカの先進企業の取り組みとも共通するんですよ。LGBTコミュニティを顧客としてしっかりと認識するということは、マイノリティの人権擁護という、それこそ社会的なコーズなのですから。ね? こうして、ウォールストリートの金融界もいま劇的に変わってきている、というリポートを、今月20日発売のバディに書いています。
さわりは次のようなもんです。
「毎年LGBTを取り巻く企業環境の優劣ランキングを調査しているゲイ人権組織ヒューマンライツキャンペーン(HRC)によると、今年9月の調査では19もの企業が100点満点を取った。4年前はJPモルガンただ1社だったのに。市場価値で上位5社に入る米国の証券会社で満点を取らなかったのはこの調査に参加しなかったベア・スターンズ社だけだ。」
面白そうでしょ? お読みくださいな。