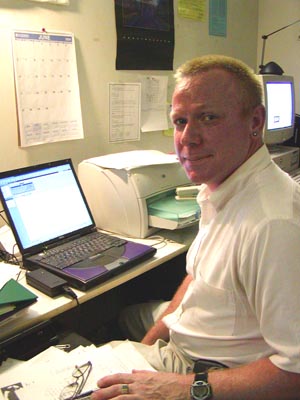「国家の品格」というトンデモ本
日本から来た若い友人が、どうぞ、とある新書を置いていきました。数学者藤原正彦さんがお書きになった「国家の品格」(新潮新書)という本でした。日本ではもう110万部も売れているのだそうです。ざっと通読後、私の尊敬する友人である若いお医者さんとかまでもが激賞しているのを知り、え、そんな感動するような本だったかしら? と思って、そりゃもういちど精読したほうがいいかなと思ってそうしたのですが、やはりこんども冒頭からつまずいてしまいました。

こう書いてあるのです。「30歳前後のころ、アメリカの大学で3年間ほど教えていました」「論理の応酬だけで物事が決まっていくアメリカ社会がとても爽快に思えました。向こうではだれもが物事の決め方はそれ以外にないと思っているので、議論に負けても勝っても根に持つようなことはありません」
おいおいちょっと待ってよ。アメリカでだって「論理の応酬」だけでなんか物事は決まらないし「議論に負けても根に持たない」という見方も単純すぎます。そんなロボットみたいな人間、いるわけないじゃないですか。ちょっと考えただけでもそのくらいはわかる。そんなのとっても中途半端なものの見方で、あまりに情緒的に過ぎませんか。
首を傾げながら読み進めると、そんな筋運びばかりでした。欧米式の「論理」だけではダメだ、日本的な「情緒」と「形」こそが重要なのだという“論理”なのですが、「論理だけでは駄目だ」が、いつのまにか「論理は駄目だ」にすり替わって、その対極とする日本的「情緒」の価値を持ち上げる、という仕掛けでした。
もっとも、ここで藤原さんがおっしゃる「情緒」というのは「喜怒哀楽のようなだれでも生まれつき持っているものではなく、懐かしさとかもののあわれといった、教育によって培われるものです。形とは主に、武士道精神から来る行動基準」だそうなんですが。
でもしかし、ふむ、ちょっとよくわからない。
そもそも「論理」というのは方法・メディアであって日本的「情緒」という実体概念・共同幻想とは対にはならないでしょう。次元が違うのです。だって、情緒にだって論理はある。花伝書なんてその最たるものです。近松の虚実皮膜論だって見事なものだ。芭蕉にも種々の俳諧論があります。したがって日本的情緒の根源も論理で説明しようとする努力は歴史的にも否定されるものではありません。論理と情緒は敵対する水と油ではないのです。「論理」に対抗するのはこの本ではむしろ「形」の方でしょう。
さてこうして筆者はゲーデルの「不完全性定理」まで持ち出してきて徹底的に「論理」を批判します。たとえば57ページには「風が吹けば桶屋が儲かる」という“論理”を、現実には桶屋は儲からない、と結論づけて、だから長い論理は危険だ、とわたしたちに言い含めます。
ここでまたわからなくなる。
だって、風が吹いてもじっさいには桶屋は儲からない、という結論自体もまた筆者の嫌う「(長い)論理」によって導かれた結論なのです。しかしそれには触れずに、つまり、論理はダメだということを論理によって説明しているのに、さらにつまり、筆者は論理の有効性を知ってそれを利用して結論づけてもいるのにもかかわらずそれには頬かむりして、だから論理はダメだ、だから情緒だ、と論を持っていくのです。
もちろん筆者もバカじゃないですから(いやむしろかなり頭の良い方なんでしょうね)、何度も「論理を批判しているのではない」「論理だけでは駄目だといっているのだ」と断りを入れてはいるのですが、そういう「論理だけでは世界が破綻する」というきわめてまっとうな物言いを、ところが読者は限りなく「論理では世界が破綻する」という意味合いに近く誤読するよう誘導される書き方なのですね。
これって、都合のよいところだけ論理的で、都合の悪いところはまるで手抜きの論証ではないか。いや、違う……都合の悪い部分は「論理」だと言って、都合の良い部分はそれは「情緒」だと依怙贔屓しているのか……。牽強付会は日本的情緒に最も反する行為なのに。
先ほども言ったように「情緒」に対抗するものは「論理」ではありません。「情緒」に対して批判されるべきはむしろ「ゲーム」という概念です。藤原さんの厭うのは、「アメリカ化」が進んだ末の「金銭至上主義」による「財力にまかせた法律違反すれすれの」「卑怯」で「下品」な「メディア買収」に象徴される「マネーゲーム」だと、ご自身でもわかっていらっしゃるのに(p5)。この「ゲーム」の感覚に対抗するために、本来ならば「論理」を攻撃するのではなく、情緒と論理の2つの力を両輪にすべきなのに。
さて先ほど、「論理」に対抗するのはこの本では「形」の方だ、とも書きました。
藤原さんはそれに関していじめの例を引きます(p62)。武士道精神にのっとって「卑怯」を教えないといけない、と説くのです。
「卑怯」というのは、「駄目だから駄目だ」らしい。それを徹底的に叩き込むしかない、という。「いじめをするような卑怯者は生きる価値すらない、ということをとことん叩き込むのです」とまで力説します。もっとも、何が「いじめ」かについては触れられません。そうしてこの「駄目だから駄目」「ならぬことはならぬのです」(p48)という武士道精神的「形」を子供にまず押し付けなければならないと言うわけです。
それは「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いかけにも同じだそうです。「駄目なものは駄目」「以上終わり」だ、と。
ところで、武士道というのは「人を殺す」ための教えです。ここでまたまたわからなくなります。
藤原さんの「なぜ人を殺してはいけないのか」への答えは、藤原さんの敬愛する「武士道」精神では「駄目なもの」ではない。いったい、その「駄目なもの」の基準はどこにあるのか。「いじめ」もそうですけれど、それは時代や文化や場所によって異なるものなのです。普遍的な基準などない。だから懸命にそれを考えるのです。
「駄目なものは駄目」という話を聞くと私はいつも「廊下を走ってはいけません」という小学校のときの規則を思い出します。小学校の先生というのはあまり深いことを教えてくれません。なぜ廊下を走ってはいけないのか? それは規則だから。なぜ喧嘩をしてはいけないのか、それは規則だから。なぜ人を殺してはいけないのか、それは規則だから。
で、友だちが大けがをして先生を呼びにいくときも、走らずに歩いていく子供が生まれるのです。「なぜ」という「論理」を考え続けない限り、そうしたやさしい日本的「情緒」の生まれる土壌さえ作れないのです。
人を殺してはいけない、これは論理ではない、と藤原さんは言いますが、これだって論理です。なぜ人は殺してはいけないのか、という反語は「じゃあ、殺してやろうか?」という反問を有効にするからです。すると自分が殺されてもよい状況が生まれます。そのとき、その自分は殺されるので人を殺すことができなくなります。だから人殺しは不可能なのです。「なぜ人を殺してはいけないのですか」と質問されたら、ですから「じゃあ、殺してやろうか」という答えが,論理的に必然的に待っているのです。
それから先の論理は自分で考えてもらいましょう。
では、武士はなぜ人を殺してよかったのか? それはなぜなら、自分が殺されてもよかったからなのです。もちろんそれはある一面ではありますが、それでもこれは1つの論理の導く1つの結論です。武士道もまた、じつに武士道的に論理的なのです。
「駄目なものは駄目」というのが、じつは私はとても苦手です。生理的に駄目なのです。そういう意味ではまことに「駄目なものは駄目」は駄目です。
というのも、それを認めると「理不尽」が通されてしまうからです。こういうことを書いている本を、たとえば同性愛者の人がすこしでも評価するというのはいったいどういうことなのかと考えてしまいます。
ええ、ゲイの若い人たちの中にもこの本を賞賛する人がいます。同じ論理が、いや、ここでは物言いと呼びましょうか、「ゲイ」と呼ばれる者たちに向けて公然と抑圧として発せられてきた歴史を知っているはずの彼らが、この記述をスルーするのはなぜなのでしょうか? 「駄目なものは駄目」「気持ち悪いものは気持ち悪い」「罪なものは罪」。問答無用。そんな物言いを、認めるのですか? 私にはそれはどうしてもできない。
藤原さんのこの本にはじつは政治や経済に関するごく基本的なことに関しての誤解や誤謬も数多くあります。まあ数学者だからしょうがないのかもしれません。しかし、この「駄目なものは駄目」に象徴される論の運びは私には看過できない。
どうして若い人たちがこの本をよいと言うのか、その辺を考えると、なんだか日本人としての自分のアイデンティティをくすぐられるという、そういう昔ながらのエサが随所にちりばめられているせいではないかとも思います。
はかないものに美を感ずるのは日本人特有の感性だというドナルド・キーン(p101)。随筆「虫の演奏家」で日本人は庶民も詩人だと書いたラフカディオ・ハーン(p102)。日本の楓は欧米のと比べて非常に繊細で華奢で色彩も豊かだと気づいて感嘆したフィールズ賞も貰っているケンブリッジ大学の数学の教授(106P)等々。
なるほどこういうのは日本人として読んでいて心地はよいですが、でもそういうのは欧米人特有のお世辞なんですよ。
英語の「コンプリメント」は日本語のお世辞と違ってウソの要素はないですが、強いて美点を探し出してそれを強調するのが基本。その分を割り引かずに真に受けて鼻の穴を膨らませるのはあまりに子供っぽい反応でしょう。もちろんこちらとてそれらに関する矜持はありますけれど、それは西洋人にお墨付きを貰わなくともよい。ふむふむ、と聞いているくらいでよいのです。そんな世辞で夜郎自大にならないこと、それこそ謙譲の美徳というものです。
総じてこの本は、日本という国にもっと誇りが持てるような、あるいは誇りを持つことを励ますような記述にあふれているのですが、思うに日本人ほど自分の国を特別な国だと思っている(思いたがっている)国民はほかにいないんじゃないでしょうか? 逆に言えばどうしてこうも情緒だもののあわれだ武士道だ、といつも確認していなければ自信を持てないのか。どうして特別だと思わなければやっていけないのか。そのへんの自意識のさもしさが,私には品格に欠けると思わざるを得ないのです。
「虫」の音を「ノイズ」と呼ぼう(101P)が、「サウンド」と呼ぼうが、バッハやモーツァルトやベートーベンやチャイコフスキーを生んだ「西洋人」の音楽性を否定するわけにはいきません。虫の音をノイズと呼んだくらいで、日本人の音楽性やもののあわれのほうがすぐれているとは、論理的にいってわたしにはどうしたって断言できない。儚さを包み込んだラフマニノフのもののあわれは、じゅうぶんに紫式部とも張れるものだと思うし、秋の日のヴィオロンの溜め息の身に沁みて、と謳ったベルレーヌだって、じゅうぶんにもののあはれではないですか。
この「おあいこ」の感じ、これを大切にしたいのです。日本だけが特別で、すごいのではない。いや、すごくて特別なところはもちろんありますよ。私はそれは密かに自負もしてます。言えといわれれば日本の特別で素晴らしいところなど10や20はすぐにでも言えます。でも言わない。かっこ悪いもの。それに、同じように諸外国にもすごくて特別なところがあるって知っているし。その畏れを大切にしたい。私たちはその国の人じゃないからそれを知らないだけなのです。詳しくも知らないし、その感覚の基となる気候や文化や歴史だってそこに生きている人ほどには知りようもない。次元は違うかもしれませんが、いろんな国の人がみな自分の国や文化をそう思っているのだと思いますよ。そんな他者への畏れを、私はいろんなところに行きいろんな人に出逢っていろんな話を聞いて、持つようになりました。ジャーナリストをしていてよかったと思うのはまずそこです。しかも会社の金で世界中の人たちと会えたし、はは。
以前にも書きましたが、愛国心、祖国愛というのはどの人にもだいたい共通のものです。そうしてそれは論理的でなくなり、感情的になるときにイビキに変わる。自分のは気にもならないが、隣のヤツのはひどく耳障りになるのです。
この「国家の品格」は一事が万事この調子でした。きっと「欧米人」が読めたらイビキとか歯ぎしりとかの類いにしか聞こえないような。論の大前提がとても単純化された虚構なのです。先ほども触れたように、さらには藤原さんもご存じのように(p122)、もともとは鎌倉武士の戦いの掟である「武士道」というものと新渡戸稲造の説いた「武士道」とは違うものです。新渡戸武士道が大いなる虚構だというのはいまや常識なのに、それを敢えて前提に持ってきたのは数学でいう「前提が偽なら結果はすべて真」という論理を拝借した結果なのでしょうか。
武士道に絡めて、もう1つ言ってよろしいですか?
新渡戸武士道の最高の美徳は「敗者への共感」「劣者への同情」「弱者への愛情」(p124)だそうなんです。そこで差別に関して、藤原さんは「我が国では差別に対して対抗軸を立てるのではなく、惻隠の情をもって応じました。弱者・敗者・虐げられた者への思いやりです。惻隠こそ武士道精神の中軸です。人々に十分な惻隠の情があれば差別などなくなり、従って平等というフィクションも不要となります」(p90-91)といっていますが、この「惻隠の情」、主語はだれなんでしょうか? そう、武士です。
敗者、劣者、弱者という人々は惻隠の情を持ち得ない。あくまで、惻隠の情を持ってもらう,抱いてもらう立場のままです。
この武士道精神は、藤原さんが「非道」(p21)と批判している帝国主義・植民地主義とまったく同じ思考方法です。おまけに「人々に十分な惻隠の情があれば差別などなくなり、従って平等というフィクションも不要となります」と言うその同じ口で、その2ページ前と7ページ前に、「国民は永遠に成熟しない」「国民は賢くならない」とも断言しているのです。
頭がこんがらがってきませんか? この「国民」と「人々」とは別な存在なのでしょうか? 「人々」とは武士的な人、のことなのでしょうか? まさに、選ばれてあることの恍惚。でもそこに不安はないようです。
藤原さんの言い方では、武士だけが主語になれるのです。オンナ、コドモやオカマやカタワは常に「惻隠の情」の目的語の位置から逃れられない。そんな定型な「形」は、押し付けられても困ります。万物は流転するのです。日本的情緒の権化である鴨長明だってそういっている。
私はいまの日本に欠けているのは(そしてこの本にも欠けているのは)むしろ丁寧な論理の紡ぎ方の教育だと思っています。だいたい論理というものが日本で人気のあったためしはありません。面倒くさいですからね。それに対して、情緒という言葉の響きの、なんと情緒的で安易なことか。受けるはずです。
この本は、じつは第4章以降はまともすぎるほどにまともです。筆者の説く「徹底した実力主義は間違い」「デリバティブの恐怖」「小学生に株式投資や英語を教えることの愚劣さ」「ナショナリズムは不潔な考え」などの結論はまったくもって私の考えと同じです。
ですがそこに辿り着くまでの論の運びは、私には大いなるブラックジョークとしか読めませんでした。もっとも、その一人漫才ぶりがこの本の売りなんでしょう。
そういうことです。
ずいぶん長く書きました。それもこれも、こんな本に簡単に感動しているきみに、私の思いを伝えたかったからです。この本は、ぜひジョークとしてお楽しみください。そうすればまあ可笑しいし、随所で何度かは吹き出したりもできます。
以上、終わり。(2006年4月のブログ Daily Bullshit から)